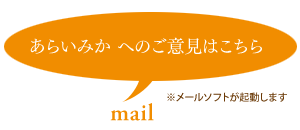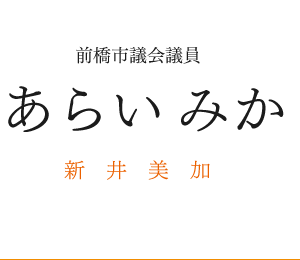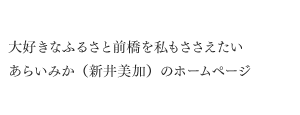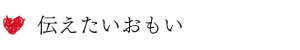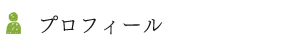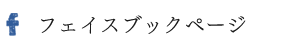忘れてはいない。いつも。パート2
2024.02.02 <日記>
K候補は「世の中には心底悪い人はいない」という持論でした。
しかし、居るのです。
「悪い人はいるのです」
ダースベーターのような一族はいる。
K先生は負けた。
「彼に流れている血がわからない」
そう言い残して。
それからしばらくしてk先生は逝った。
忘れない。いつも。
たかが、文章だけでも人を死に追いつめる。
だから戦う。
忘れてはいない。いつも。パート1
2024.02.01 <日記>
K先生の市長選挙は現職市長との一騎打ちだった。
私はまだ若く、選対とはいえ、市議でもなんでもない肩書きのないひとりの支援者に過ぎなかったが、
インターネットを駆使する選挙などまだなかった時代でもあったが、小さな企画会社をしていた私は、
自称「ネット部隊」をつくり、相手候補をネット上でチェックしていた。
選挙戦の火蓋が開き、
突然、現職市長側のブログに目を疑うような、K先生を侮辱する文章が書かれているのを発見し、
その文章をコピーして候補や選対幹部に見せても、当時はネットのブログの文章にそれほどの威力があるとは、誰も思わない時代
誰にも私の忠告は相手にされなかった。
その文章はK先生の市長選挙を最後まで苦しめることとなることをまだ誰も知らなかった。
またまた「おせっかいぐせ」が・・・
2023.08.31 <日記>
昨日、市役所の国民年金課の窓口に腰掛けて、色々とアドバイスを受けていたら、隣の窓口からかすかに聞こえてくる声。
盗み聞きをしたわけじゃないのだが、たまたま聞こえてきたその内容が
「今まで、主人からDVを受けていて、外に出ることも禁止されていて、もちろんお金も自由にならず、国民年金を払っていないので、少しづつでも払いたい」
小さな声なので、よく聞き取れなかったが、必死で訴えているその部分の言葉だけは、私の耳がキャッチした。
私の「おせっかい」アンテナがビビっときた。
ちらっと見ると、なんとも美しい横顔。
疲れてやつれているものの、なぜ、こんな可憐な人が、DVなんか受けるのだろう?
守ってやりたいとは思わないのか・・・
さすがの「でしゃばりみかばーさん」も隣の窓口の市民の方に唐突に話しかけるわけにもいかず・・・
しかし、その夜、やはり私は気になって眠れずにいた。
今、私が理事長として申請しているNPOはまさにこういった方達の最初の相談窓口となるべくあたためてきた企画である。
総括質問 9月定例会 こども未来部の新設について
2023.07.24 <日記>
1 こども未来部の新設について
(質問)
6月13日に国が決定した「こども未来戦略方針」では、異次元の少子化対策となる今後3年間のこども・子育て支援加速化プランとして、中学卒業までが対象だった児童手当を「18歳になった後の3月末まで」 に拡充し、育児休業給付を25年度から休業前の手取りの実質10割に上げるなどの経済的支援の強化や、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充などが掲げられている。
今年4月に国のこども家庭庁設置と同時に、本市でもこども未来部が設置されたところだが、本市のこども施策の推進体制について伺います。
(答弁)
少子化は、我が国が直面する最大の危機であると言われております。この危機に対応するため、国ではこども家庭庁を設置し、本市においても、こどもや子育てに特化したこども未来部を設置したところでございます。
こども未来部の設置に当たっては、従来からの児童福祉部門と母子保健部門の連携を更に強め、専門職を始めとする職員の増員なども行い、妊娠期から子育て期に渡る総合的な支援を行う体制を強化いたしました。
この新たな体制によって、国による「次元の異なる少子化対策」に迅速に対応するとともに、本市のこども施策を強力に推進していけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
(質問)
少子化は最大の危機状態にあることは間違いないと思います。
そこで質問します。
①これまでの実施状況について
国が新たな出産、子育て支援策として打ち出した出産・子育て応援給付金事業は、妊産婦への伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金を一体的に実施する事業であり、本市では令和5年1月から開始されているが、これまでの実施状況について伺います。
(答弁)
出産・子育て応援給付金事業についてでございますが、国が昨年12月に実施を決定したことを受け、本市では、県内自治体の中でも先駆けて、今年1月に開始いたしました。
まず、妊産婦に対する伴走型相談支援につきましては、本市では、本事業開始前から、妊娠届け出時と出産後のすべての方に保健師等が面談を実施し、寄り添った支援を行っておりました。本事業の開始に伴い、妊娠8か月頃の全妊婦を対象に、出産に向けた悩みや心配な事項を確認することが追加され、よりきめ細かい支援内容として、実施しているところでございます。
出産・子育て応援給付金の支給状況につきましては、本市では速やかに事業を開始するため、現金により指定の口座に支給す
ることとした結果、令和4年4月1日から事業開始前までに妊娠届又は出生届を出された経過措置対象者の96%以上、4,365人に支給を終えております。
また、今年1月の事業開始以降に対象となった方につきましても、順次申請を受付け、3月末までに594人の方に支給いたしました。
(質問)
出産・子育て応援給付金事業については、本市では、県内自治体の中でも先駆けて、今年1月に開始したということで、早い対応であり、現金により指定の口座に支給することとした結果、令和4年4月1日から事業開始前までに妊娠届又は出生届を出された経過措置対象者の96%以上、4,365人に支給を終え、
今年1月の事業開始以降に対象となった市民に対しても、順次申請を受付け、3月末までに594人の市民に支給されたとのことですので、
今後も他市の見本になるような対応をお願いします。
妊産婦に対する伴奏型支援についても告知の必要性があると思います。身重の身体である妊婦や忙しい子育て中の母親が情報を得る手段として
スマホで、前橋市のこども未来部を検索すると、「こども支援課」と「こども施設課」が突然でてくる感じで、目的がある場合はいいですが、
課の内容の案内が出てくるといいと思いますね。
Hpが見ずらいというのは子育て中の方々にはつらいかな。。。と思います。
出産・子育て応援給付金と検索するとそのページにいきますが、「なにか市民に対しての補助はあるかしら?」と悩んで、検索した場合に簡単にたどりつけるようなコンテンツを研究していただきたいです。
本市では、給付金は、現金支給としているが、国は使途を子育て目的に限定でき、より消費につながりやすい電子クーポン等による電子的な方法の活用を検討するよう要請している。本市の見解を伺います。
(答弁)
本市では、まずは対象となる妊産婦の方に速やかに給付金を支給することを最優先し、現金による支給とした結果、経過措置分の支給対象者を含め、迅速、かつ、円滑に事業を開始することができました。
電子的な方法による支給については、国からの要請を踏まえ、庁内の関係課とともに検討を進めてきたところですが、本市での電子地域通貨の導入に合わせ、電子地域通貨による支給へ移行させたいと考えております。
染谷川に架かる橋、地元の悲願。もうすぐ完成。
2023.06.21 <日記>
7 西部第一落合土地区画整理事業について
(質問)
(1) 仮設道路の整備予定と課題
西部第一落合土地区画整理事業について伺います。
西部第一落合地区において現在整備が進んでいる橋梁については、地元住民の注目度も高く、今年夏の完成にあたり、これから本格的に地区内の整備が始まっていくものと実感しております。
先日の総括質問の答弁において、橋梁工事が完了した後に仮設道路を設置すると伺いました。これにより、今まで地区内に進入が難しかった建設機械等の出入りが可能になり、整備の進捗が図られるものと考えます。
しかし、仮設道路は事業で計画している都市計画道路や区画道路とは異なり、事業進捗のための道路であることから、地権者等関係権利者の理解を得るには簡単ではないと感じているところです。
そこで今後の仮設道路の予定と、設置にあたっての課題を伺います。
(答弁)
仮設道路の予定ですが、現在は、設置予定箇所の用地確保を建設中の橋梁側から順次行っており、その進捗状況により出来るところから着手してまいりたいと考えております。
また、整備に対する課題についてですが、予定箇所は盛土が必要な箇所があり、盛土周辺低地の雨水排水と、仮換地指定前に用地を使用させてくださるよう、地権者等関係権利者に対しご理解とご協力を得られるよう努めると同時に適正な補償が大事と考えております。
(質問)
(2)西部環状線の整備予定
仮設道路については承知いたしました。
その仮設道路と建設中の橋梁を利用することで、地区内への進入が容易になり、現在の西部環状線に建設機械等のアクセスが可能になるものと考えます。
西部環状線については、本地区と蒼海地区との間においても街路事業として整備に向けた準備が進められており、早期の開通に地元も期待しているところです。
そこで、地区内における西部環状線の今後の整備について伺います。
(答弁)
地区内における西部環状線の整備予定についてですが、現在関係権利者と仮換地指定に向けた調整を行っている段階です。一定区間の仮換地指定と建物等の移転を行い、道路用地を確保して、雨水排水や、下水道の整備に着手してまいります。
令和5年第1回定例会 建水委員会 【新井 美加 委員】
(質問)
(3)来年度の整備予定
新しい橋梁の当面の利用方法と仮設道路の位置づけについての答弁を受け、西部環状線をはじめ区画整理事業の整備方法についても理解が深まってきました。
これから本格的な着手となり、確実に整備が進んでいくことと期待しております。
さて、先日の総括質問の答弁においても、西部環状線と併せて雨水排水の流末である調整池を優先し整備を進めるとのことですが、増加するゲリラ豪雨にも対応し、円滑に事業を進めていくためにも、雨水排水は最重要課題であると考えます。
調整池の整備に向けて、これから関係権利者に理解を得ながら用地確保を行い、早期に整備しなければならないと思いますが、来年度の整備予定について伺います。
(答弁)
調整池部分の用地を確保するため、地権者等と調整を行い、仮換地指定を行いながら順次移転をお願いしてまいります。
段階的な整備として来年度においては、調整池予定箇所北側の建物等の移転に伴う宅地造成工事と道路側溝等の整備を行う予定でございます。
(要望)
西部環状線をはじめ区画整理事業の整備方法、合わせて調整池を優先して整備するとのこと。総括質問では聞けなかった詳細な部分をお聞きしました。
地元の方々の長い間の悩みごとの解決のためにしっかり進めていっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
2023.05.31 <日記>
久しぶりの建設水道常任委員会 仮設道路の整備予定と課題
2023.04.27 <日記>
西部第一落合土地区画整理事業について、西部環状線の整備予定について等、
長年の懸案が動き出します。
久しぶりの建設水道常任委員会で質問いたしました。
西部第一落合土地区画整理事業について
(1) 仮設道路の整備予定と課題
(質問)
西部第一落合土地区画整理事業について伺います。
西部第一落合地区において現在整備が進んでいる橋梁については、地元住民の注目度も高く、今年夏の完成にあたり、これから本格的に地区内の整備が始まっていくものと実感しております。
先日の総括質問の答弁において、橋梁工事が完了した後に仮設道路を設置すると伺いました。これにより、今まで地区内に進入が難しかった建設機械等の出入りが可能になり、整備の進捗が図られるものと考えます。
しかし、仮設道路は事業で計画している都市計画道路や区画道路とは異なり、事業進捗のための道路であることから、地権者等関係権利者の理解を得るには簡単ではないと感じているところです。
そこで今後の仮設道路の予定と、設置にあたっての課題を伺います。
(答弁)
仮設道路の予定ですが、現在は、設置予定箇所の用地確保を建設中の橋梁側から順次行っており、その進捗状況により出来るところから着手してまいりたいと考えております。
また、整備に対する課題についてですが、予定箇所は盛土が必要な箇所があり、盛土周辺低地の雨水排水と、仮換地指定前に用地を使用させてくださるよう、地権者等関係権利者に対しご理解とご協力を得られるよう努めると同時に適正な補償が大事と考えております。
(2)西部環状線の整備予定
(質問)
仮設道路については承知いたしました。
その仮設道路と建設中の橋梁を利用することで、地区内への進入が容易になり、現在の西部環状線に建設機械等のアクセスが可能になるものと考えます。
西部環状線については、本地区と蒼海地区との間においても街路事業として整備に向けた準備が進められており、早期の開通に地元も期待しているところです。
そこで、地区内における西部環状線の今後の整備について伺います。
(答弁)
地区内における西部環状線の整備予定についてですが、現在関係権利者と仮換地指定に向けた調整を行っている段階です。一定区間の仮換地指定と建物等の移転を行い、道路用地を確保して、雨水排水や、下水道の整備に着手してまいります。
(質問)
(3)来年度の整備予定
新しい橋梁の当面の利用方法と仮設道路の位置づけについての答弁を受け、西部環状線をはじめ区画整理事業の整備方法についても理解が深まってきました。
これから本格的な着手となり、確実に整備が進んでいくことと期待しております。
さて、先日の総括質問の答弁においても、西部環状線と併せて雨水排水の流末である調整池を優先し整備を進めるとのことですが、増加するゲリラ豪雨にも対応し、円滑に事業を進めていくためにも、雨水排水は最重要課題であると考えます。
調整池の整備に向けて、これから関係権利者に理解を得ながら用地確保を行い、早期に整備しなければならないと思いますが、来年度の整備予定について伺います。
(答弁)
調整池部分の用地を確保するため、地権者等と調整を行い、仮換地指定を行いながら順次移転をお願いしてまいります。
段階的な整備として来年度においては、調整池予定箇所北側の建物等の移転に伴う宅地造成工事と道路側溝等の整備を行う予定でございます。
(要望)
西部環状線をはじめ区画整理事業の整備方法、合わせて調整池を優先して整備するとのこと。総括質問では聞けなかった詳細な部分をお聞きしました。
地元の方々の長い間の悩みごとの解決のためにしっかり進めていっていただきたいと思います。
長年の懸案 西部環状線 溢水対策 定例会での質疑応答
2023.03.26 <日記>
6 西部環状線現地測量等について
(質問)
(1) 路線概要
都市計画道路西部環状線は、西部第一落合地区の土地区画整理事業による道路整備にあわせて、未整備の区間を街路事業として整備を開始する予定であり、まず令和5年度内に現地測量を行いたい旨、先日開催された地元説明会にて伺ったところである。
路線および事業の概要について伺います。
(答弁)
西部環状線の路線概要についてですが、本路線は古市町から総社町総社に至る全長約3,160m、幅員22mの都市計画道路です。全区間のうち、4車線区間である主要地方道前橋・高崎線から国道17号までの区間及び2車線区間のうち元総社西部第三明神地区土地区画整理事業区域内が整備済みであり、元総社蒼海地区土地区画整理事業区域内及び西部第一落合地区土地区画整理事業区域内が現在整備中となっております。
事業概要につきましては、未整備区間のうち、県道足門前橋線から主要地方道前橋安中富岡線までの約360mの区間を街路事業として整備するものです。
(質問)
(2) 課題と整備見込み
都市計画道路西部環状線の路線及び事業の概要については理解した。この路線の整備は地域住民の悲願であり、西部第一落合地区の道路整備を併せると道路ネットワークの整備効果は非常に高く、元総社地区全体の整備の気運が高まっていくものと思われ、早期の整備が望まれる。
整備に向けた課題とその対応、整備時期の見込みについて伺います。
(答弁)
西部環状線の整備に向けた課題は、現時点ではゲリラ豪雨等の際の溢水対策、および用地買収により移転を余儀なくされる地権者の生活再建と認識しています。対応について、溢水対策は今後行われる調査、設計の中で効果的な整備手法を検討してまいります。また地権者に対しては今後の調査や説明の際に要望を十分に伺い、こちらから対応策を提案していくことにより生活再建に繋げてまいりたいと考えております。
次に、整備時期の見込みは、令和5年度に事業認可を取得し、現地測量等の作業を経て令和7年度には用地買収に着手し、その後可能な箇所から拡幅工事に取り掛かる予定です。事業が順調に進捗すれば概ね令和15年頃に供用開始となる見込みです。